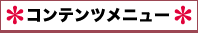
広島大学男女共同参画推進室 女子中高生の理系進路選択支援プロジェクトのトップページです。
科学技術分野で活躍する女性研究者・技術者、大学生等と女子中高生の交流機会の提供や実験教室の実施等、女子中高生の理系進路選択を支援する取組を実施します。
女子中高生が実験・学習できる科学教室を実施します。
理系分野のキャリアをイメージするために、理系分野の職業で活躍している先輩女性との交流や職業見学を実施します。
広島近辺で開催される様々な理系イベントのお知らせや、理系への進路選択に関する情報を発信します。
取り組みに対するご質問、科学に対する疑問にお答えします。
事務局概要、ご相談、お問い合わせ、ご意見、ご要望はこちらです。
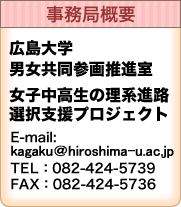 広島大学男女共同参画推進室 女子中高生の理系進路選択支援プロジェクト 事務局概要
広島大学男女共同参画推進室 女子中高生の理系進路選択支援プロジェクト 事務局概要

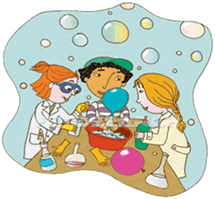
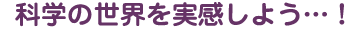
女子中高生のための科学教室に参加して、あなたも活躍できる科学の世界を実感して
みませんか?
平成21年度は、女子中高生のための科学教室(工学編)、(理学編)、(総合科学編)の3回を実施しました。
女子中高生のための科学教室(工学編)
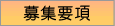
| 日時/場所 |
日時: 平成21年8月8日(土) 12:00-17:00
場所: 広島大学工学部 |
| 定員 |
30人程度 ※保護者や教員の方の参加も、歓迎します。 |
| 申込み締切り |
平成21年7月10日(金) 終了しました。 |
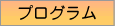
| 12:00 |
受付開始 (工学部B棟117号室前) |
| 13:00 |
コアコースの実習を体験します。 |
| 14:50 |
サブコース1-3の中から、1つの実習を体験します。 |
| 16:30 |
質問コーナー |
| 17:00 |
解散 |
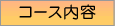
コアコースの実習と3つのサブコースの中の1つのサブコースの実習を工学部で体験します。
| ●コアコース (全員が参加します) |
|
<テーマ> 太陽エネルギーを活用した有用物質のバイオ生産
<担 当> 加藤 純一 教授 (広島大学大学院 先端物質科学研究科)
中島田 豊 准教授 (広島大学大学院 先端物質科学研究科)
柿薗 俊英 准教授 (広島大学大学院 先端物質科学研究科)
<場 所> B4棟地階 実験室004室
<内 容> 工学部のバイオは、優れた生物機能を発見する、その生物機能の機構を解明する、さらに優れた機能に育て上げる、そして育て上げた生物機能を活用する、教育・研究が特色です。 この体験実習では、微細藻類を活用した生理活性物質の生産について体験していただきます。 ある種の微細藻類は、CO2、H2Oおよびミネラルを主原料、そして太陽光をエネルギー源として抗酸化作用のあるバイオ色素(アスタキサンチン)を生産します。 アスタキサンチンは紫外線から肌を守る効果があるため、化粧品などの添加物として利用されています。
本実習では、○微細藻類の顕微鏡観察、○微細藻類からのバイオ色素の抽出、○抽出したバイオ色素の化学分析、を行い、微細藻類によるバイオ色素の生産の一端を体験します。
|
| ●サブコース (3つのサブコースの中の1つのサブコースに参加します) |
- サブコース① (定員 10人程度)
- <テーマ> コンピュータの心臓:トランジスタの発明
<担 当> 三浦道子 教授 (広島大学大学院 先端物質科学研究科)
<場 所> 工学部B棟 114号室
<内 容> トランジスタの発明の講義を体験します。
【略歴】広島大学理学部を卒業後ドイツに渡りシーメンス社で半導体の研究をスタート。1996年帰国し、広島大学教授。日本初の国際標準のトランジスタモデルを開発。
- サブコース② (定員 10人程度)
- <テーマ> 地球をまもる小さな生き物を探し出す
<担 当> 加藤 純一 教授 (広島大学大学院先端物質科学研究科)
中島田 豊 准教授 (広島大学大学院先端物質科学研究科)
<場 所> B4棟地階 実験室004室
<内 容> 日本の土壌には非常に多種多様な微生物が住んでいます。ですから、微生物に関して日本は、世界に冠たる「資源国」です。 その微生物の中には、環境汚染物質を分解する生物機能を持つものがいます。 そうした微生物を活用すれば汚れた環境をきれいにすることもできるでしょう(バイオレメディエーション-生物環境修復-と言います)。
本体験実習では、土の中から環境汚染物質を分解する微生物を探し出す実験を体験することができます。 具体的には、
○土壌から有用微生物を単離する実験
○単離した微生物の環境汚染物質分解活性を検定する実験を行います。
- サブコース③ (定員 8人程度)
- <テーマ> 水の流れは二種類あった!
<担 当> 河原 能久 教授 (広島大学大学院 工学研究科)
椿 涼太 助教 (広島大学大学院 先端物質科学研究科)
<場 所> 工学部B棟 112号室
<内 容> 小型の開水路模型を作り、水路の真ん中にマウンドを作って、常射流の混在場などをつくり、水面形を観察する。常流と射流、跳水、支配断面などの話を、たとえば車の渋滞(常流:渋滞流れ、射流:スムーズな流れ)などと関連づけながら説明する。その後、ダムの設計や河川設計と、流れの性質の関連などについて説明を加える。
|
| ●質問コーナー |
|
<内 容> 実習で分からなかったことや理系の進路などについて、先生や学生にさまざまな質問や相談ができます。 |
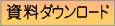


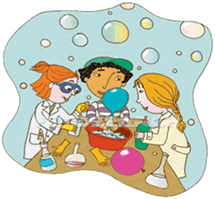
![]()
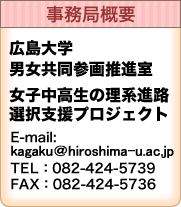 広島大学男女共同参画推進室 女子中高生の理系進路選択支援プロジェクト 事務局概要
広島大学男女共同参画推進室 女子中高生の理系進路選択支援プロジェクト 事務局概要